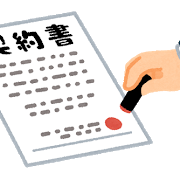
AIの開発が始まった当初は、依頼元とベンダでどう契約したらいいか非常に悩みました。
通常のシステム開発と違い、結果が確約できないからです。
ここを失敗すると依頼者とベンダのどちらかが大きな損害になります。
最近になりやっと何が良い方法なのか世間でうたわれるようになりました。
JDLA(日本ディープラーニング協会)が公開した契約書のひな型もとても良いものです。どこまで利用できるか精査したので紹介します。
AI開発が特殊な点
通常の開発と異なる点は以下です。これに留意して契約を決めることになります。
- AI開発導入の結果、業務が改善するとは限らない
- 知的財産権が発生する要素が増え(AIプログラム、学習済モデル、データセット)、それぞれ誰が権利を持つかを決める必要がある
- 開発物自体を移譲するのか、利用権を付与するのかを決める必要がある(通常の開発より意味合いが強い)
請負か委任か
開発案件では常にこの問題があります。基本的にはこうです。
請負契約: 開発内容を最後まで決めることができる場合に選択する。開発側としては瑕疵担保責任や完了責任があり重くなるが、開発進行し易い。
委任(準委任)契約: 開発範囲が決まらない、決めたくない場合、労働力を提供するような形で契約する。
AI開発は結果が分からないところがあり、また開発の過程もアジャイル開発で臨機応変に行うことが多いため、委任(準委任)契約をします。
委任(準委任)契約をする場合、契約書で委任と明記する必要はなく、「業務の詳細」ページの書き方を工夫することで実現します。委任と明記する契約書もありますが、最近はこのやり方が流行っています。
下記JDLAのひな型を利用する際も、業務詳細ページの書き方によって請負か委任かを変えましょう。
JDLA契約書ひな型
JDLAがAI開発標準契約書を公開しました。
これは筆者が使ってきた契約書と比べても遜色なく、必要な事項が網羅されています。そのまま使えそうです。
原文は下記リンクです。3種のひな型がありますが、「業務の詳細」以外は同一です。
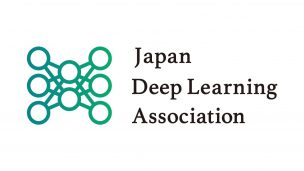
原文: JDLA「ディープラーニング開発標準契約書」
https://www.jdla.org/news/20190906001/
これを意訳し、筆者の経験から必須事項を選別しました。
なお、JDLAは大手企業がスタートアップへ依頼する形を想定していますが、通常の依頼元とベンダの関係で十分に使える契約書ですのでそのように表現しました。
| 条項 | 内容の意訳 | 必須項目 |
|---|---|---|
| 第1条(目的) | - | 必須(開発案件として) |
| 第2条(委託業務) | これは開発案件である。 | 必須(開発案件として) |
| 第3条(非保証) | AIが100%正解を出すことを保証する訳ではない。 | 必須(AI案件として) |
| 第4条(再委託) | ベンダ側はその先の企業へ再委託してもよい。 | 必須(開発案件として) |
| 第5条(本契約の変更) | 双方の合意があれば契約の変更ができる。 | 必須(開発案件として) |
| 第6条(委託者が受託者に提供するデータ・資料等) | データセットの権利は依頼側にある。違法なものではないこと。提供に不備があった場合の損失は依頼側にある。個人情報は渡さないこと。 | 必須(AI案件として) |
| 第7条(資料等の利用・管理) | ベンダ側はデータセットを目的以外で使わないこと。 | 必須(AI案件として) |
| 第8条(秘密情報の取扱い) | お互いの秘密情報は漏洩しないこと。目的以外で利用しないこと。社内の関係者以外に開示しないこと。終わったら返却または削除すること。 | 必須(開発案件として) |
| 第9条(本件開発著作物の著作権) | 著作権はベンダ側にある。依頼側で利用は可能。 | 必須(開発案件として) |
| 第10条(本件開発物等の特許権等) | 特許権は開発物を創出した者にある。AIアルゴリズムを作った場合はベンダ側にある。ベンダ側での特許物の利用は自由。 | 必須(AI案件として) |
| 第11条(本件開発物等の利用条件) | 依頼側で目的以外での利用や公開する場合は別合意が必要。依頼側で変更、逆コンパイル、モデルを利用して再生成、検出結果を学習データにして別モデルを作る、の行為は禁止。 | 必須(AI案件として) |
| 第12条(知的財産権侵害の責任) | 万が一開発物が他社の特許等を侵害した場合、ベンダ側が保証をする義務はないが援助に努めること。 | 必須(開発案件として) |
| 第13条(損害賠償) | 相手に責められるような落ち度があった場合は損害賠償ができる。 | 必須(開発案件として) |
| 第14条(契約期間) | 第3条、第6~13条、第16条(ほとんど)は契約終了後も効力がある。 | 必須(開発案件として) |
| 第15条(解除) | 相手がひどいことをしたら契約解除でき、相手は弁償の義務がある。 | 必須(開発案件として) |
| 第16条(合意管轄) | - | 必須(開発案件として) |
| 本件業務の詳細 | 契約業務の詳細と期間、金額を書く。詳細に成果物を明確に書くと「請負」の形となり、大筋で書くほど臨機応変に進める「委任」の契約になる。 | 必須(AIの要素が強く出る) |
| 覚書 | 契約書を取り交わした後、内容の追加・変更をした時に契約する書面。開発(特にAI等のアジャイル開発)では必要なもの。 | 随時(AIの要素が強く出る) |
必須項目を選ぼうとしたのですが、全て必須になってしまいました。それだけJDLAのひな型は重要事項を抑えています。
その他の考慮事項
契約書には明記しませんが、他にも意識すべき事項があります。参考までに掲載します。
- AI開発は瑕疵担保を付けない
- 収集した学習データはそのままでは知財にならない、選択や構成に創造性があるものは著作権がある
- AIプログラムに限らず開発物は作成者の著作物となる
- 学習済モデルは動作させるプログラムとセットであれば著作物となる
- 権利で揉める場合は、所有権にこだわらず利用権や利用条件で実を取っても悪くない
- 法律より契約内容が優先される、書いてないことは法律に従う
- 特別に利用権限や利用条件を決めたい物がある場合は具体的に明記する
いかがでしょうか。
AI開発も以前よりは安心して契約をすることができるようになってきました。
PoCで終わらせずに本格導入に至るよう頑張っていきましょう。
